特集:企業買収における行動指針 対談【第1回】
取締役・取締役会の行動規範・買収に関する透明性の向上を中心に(前編)
-東京大学大学院・後藤教授と、「企業買収における行動指針」の影響や今後の対応について考える-

本企画では、買収行動指針に関する幅広いテーマをトピックとして、全2回にわたり、会社法研究者と実務家との対談を行っています。このような対談を通じて、現状の実務を確認するとともに買収行動指針の理論的背景を探り、これらを踏まえて、買収行動指針が今後の実務に与える影響について様々な角度から検討を行っています。本企画が、皆様のご理解の一助となれば幸いです。
買収行動指針は、買収に関する対象会社の取締役その他の当事者についての新たな行動規範を示すとともに、近時の裁判例も踏まえて有事導入型を含む買収への対応方針・対抗措置に関する論点についての考え方を整理したものとなっており、今後のM&Aの実務に大きな影響を及ぼすものと考えられます。
「買収行動指針」に関する解説については、以下のニュースレター(全4回)をご覧ください。
目次
0.はじめに
1.企業価値における定性的な価値の考慮
Q1-1実務における定性的な事項の検討状況
Q1-2定量化できない事項の今後の取扱い
2.「買収を行わなければ実現できない価値」に関する公正な分配のための交渉の在り方(本指針2.2.2関連)
Q2シナジーの分配方法(これまでの実務と今後の対応)
3.真摯な買収提案についての考え方(本指針3.1.2関連)
Q3-1本指針で明示された考慮要素が今後の実務に与える影響
Q3-2真摯性の確認にあたり対象会社の取締役会に求められる対応
4.取締役会が買収に応じる方針を決定する場合の交渉の在り方(本指針3.2.3関連)
Q4-1本指針3.2.3の規範とレブロン義務との比較
Q4-2本指針3.2.3の規範が今後の実務に与える影響
5.マーケットチェックの在り方(本指針3.2.3関連)
Q5今後の実務におけるマーケットチェックのあるべき姿
0. はじめに
- 飛岡
-
後藤先生、お忙しいところお時間をいただき、誠にありがとうございます。経済産業省は、本年8月に「企業買収における行動指針」(以下「本指針」)を公表し、既に本指針に従ってTOBを開始した旨のプレスリリースを出している企業も見られるなど、本指針は今後のM&Aの実務に大きな影響を与えるものであると考えております。本指針の策定には、当事務所の小舘弁護士が「公正な買収の在り方に関する研究会」(以下「本研究会」)の委員として携わっているほか、私も補助者として研究会に毎回出席しておりました。
本指針については、実務家、学者、企業などの目線から様々な考え方があると思われますが、それぞれの目線からどのように対応すれば良いのか、どのような影響があるのか、我々も非常に関心を持ってここからの発展を見ていきたいと考えております。そこで、今回は後藤先生から、本指針の第3章及び第4章を中心に(第3章の取締役・取締役会の行動規範の前提となる「企業価値」の点については第2章も含めて)、ご意見をいただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
1. 企業価値における定性的な価値の考慮
本指針第2章「原則と基本的視点」2.2.2「企業価値の向上と株主の利益の確保」関連
(該当箇所の解説は、AMTニュースレター「企業買収における行動指針の概要①」6~8頁参照)
Q1-1 実務における定性的な事項の検討状況
-
飛岡経営支配権を取得する買収一般において尊重されるべき「3つの原則」のうち、第1原則における「企業価値」については、「企業価値」が定量的な概念であることが強調されている一方で、定性的な価値や非財務情報を企業価値評価に反映することも否定されない内容になっている。実務上、どのように企業価値の向上に資するか否かを検討しているのか。
➔ 分析・実務への影響
-
小舘経営者から見ると、従業員や取引先などのステークホルダーの貢献によって「企業価値」が高められていくという実感があるため、特定の買収者が現れた時には、ステークホルダーとの関係で何かネガティブなことがないかが真っ先に気になっているように思う。ステークホルダーとの関係が悪化するような場合には、それを踏まえて企業価値を毀損するという判断をすることもよく見られるが、それが将来のキャッシュフローにどのような影響を与えるかといった定量的な検討まではしていなかったのではないか。
Q1-2 定量化できない事項の今後の取扱い
-
飛岡例えば、従業員が辞めてしまう、取引先が取引を止めてしまうというところについては、それによる利益の喪失という形で定量的に織り込んでいくべきなのか、定量化できないものは別途検討していくということで問題ないのか。
➔ 分析・実務への影響
-
後藤先生定量化しなければいけないということが強く言われたのは、経営陣の保身の口実になっている面が否定できないという批判によるところがあるように思われる。従業員が辞めてしまう、取引先が取引を止めてしまうということが実際にどれぐらい起きうるのか、またそれが企業価値にどれだけの影響を与えるのかというのは、もう少し具体的に詰めていくべきではないか。また、対象会社において余剰人員を抱えている場合又は非効率な仕入れを行っている場合もありえるので、直ちに悪影響があるとは限らない。対象会社として、定性的な事情に一切言及してはならないということではないと思うが、この点からも詰めて検討する必要がある。ただ、現金対価での全部買収のオファーの場合には、買収者側の買収後の企業価値への影響を受け入れるという覚悟を示しているのだとすると、対象会社が定性的で抽象的な悪影響を主張しても、あまり意味がないと思われる。小舘実務の観点から、取引先を失うという場合の定量化について、不確定な要素が多く難しいことではあるが、できないことはないと思う。一方で、従業員の場合の定量化の方が難しく、具体的な事案の中でも、買収者が賃上げを提案していたため、コスト増になり、かえって企業価値の評価にマイナスの影響が生じてしまうということもあった。定量化ということが一人歩きするのも違和感がある。後藤先生定量化できないとしても、一切考慮してはならないということまでは求めていないと思う。それ自体が重要な情報ではあるので、株主が買収提案の是非を判断する上でも対象会社から情報提供をした方がよい。経営陣が自己保身のために反対しているのではないかという疑いは、経営陣からの情報提供の内容が詳しくなれば詳しくなるほど減っていくため、たとえ定量化できなくてもよい。その上で最後は株主の判断になる。
今後の実務上の展開・残された課題
-
本指針を受けて、企業価値の算定に際しては、対象会社においては定性的な情報や非財務情報をできるだけ定量化することが求められることになるが、こうした動きが浸透するか注目される。また、どのような内容、さらにはどこまでの範囲が、定量化が不可能又は困難なものであるとして許容されるのかは今後の課題であると思われる。
Q1-1 実務における定性的な事項の検討状況
- 飛岡
-
第2章では、上場会社の経営支配権を取得する買収一般において尊重されるべき「3つの原則」(第1原則:「企業価値・株主共同の利益の原則」、第2原則:「株主意思の原則」、第3原則:「透明性の原則」)が提示されています。第1原則における「企業価値」については、「公正なM&Aの在り方に関する指針」(以下「公正M&A指針」)における考え方と同じく、「企業が将来にわたって生み出すキャッシュフローの割引現在価値の総和を表すものである」ことを改めて確認した上で、さらに踏み込む形で、「企業価値は株主価値と負債価値の合計として表される」と整理し、「企業価値」が定量的な概念であることが強調されています。さらに、本指針では、「対象会社の経営陣は、測定が困難である定性的な価値を強調することで、『企業価値』の概念を不明確にしたり、経営陣が保身を図るための道具とすべきではない」とされており、できる限り定量的に判断すべきであることが強調されています。
一方で、本指針は、従業員や取引先などのステークホルダーの貢献や、地域社会や地球環境との関係などを含む非財務情報も企業価値の評価に反映することも否定されない内容になっています。
そこで、まずは小舘弁護士にお聞きしますが、実務家の目線から、対象会社として買収提案を検討する際に、定性的な価値や非財務情報を重視して企業価値の向上に資するか否かを検討した事例があったか、そのような事例があった場合には具体的にどのような項目を検討したのかなど、実務における、定性的な事項の検討状況についてご説明いただければと思います。
- 小舘
-
実務上、もちろん株主価値についても検討しますが、まずは企業価値の向上に資するか否かを検討しています。本指針においても、「企業価値ひいては株主共同の利益」と従来と同じように表現されています。おそらく、取締役の善管注意義務は会社に対する義務であるという伝統的な考え方から来ていると思っております。
経営者から見ると、従業員や取引先などのステークホルダーの貢献によって「企業価値」が高められていくという実感があるため、特定の買収者が現れた時には、ステークホルダーとの関係で何かネガティブなことがあるのではないかということを真っ先に気にするように思います。実務上、ある買収者が経営支配権を取得したら従業員が辞めてしまう、取引先が取引を止めてしまうというような形で取り上げることは比較的多いと思っております。
このような場合でも、これまではステークホルダーとの関係について、定量的に検討することはあまりなかったのではないかと思います。例えば、従業員又は労働組合から反対声明を出す、取引先の団体から反対声明を出すといったことはよくあり、それを踏まえて企業価値を毀損するという判断をすることもよく見られますが、それが将来のキャッシュフローにどのような影響を与えるかといった定量的な検討まではしていなかったのではないかと思います。
Q1-2 定量化できない事項の今後の取扱い
- 飛岡
-
これまでも定性的な価値については企業価値の向上に資するか否かの検討において考慮されていたが、それを十分に定量的なものへ反映することはできていなかったというのが実務の現状であるかもしれません。今のご説明を踏まえて、後藤先生にお聞きしますが、本指針は、できる限り定量的に判断すべきだというところを打ち出していると考えていますが、例えば、従業員が辞めてしまう、取引先が取引を止めてしまうという点については、それによる利益の喪失という形で定量的に織り込んでいくべきなのか、定量化できないものは別途検討していくということで問題ないのか、この点に関する本指針の考え方についてのご意見を頂戴できますでしょうか。
- 後藤先生
-
本指針において、定量化しなければいけないということが強く言われたのは、対象会社の経営陣の保身の口実になっている面がどうしても否定できないという批判によるところがあるように思います。
対象会社の経営陣としては、従業員が反対していることから、ステークホルダーの利益及び企業価値を害すると主張することは簡単ですが、抽象的にそのように主張するだけではなく、具体的にどれだけの悪影響があるかということを、やはりしっかりと考えなければならないということだと思っております。もちろん、具体的な企業価値への影響を金額で算定することまでは難しいということはあると思いますが、例えば、小舘弁護士がおっしゃった、従業員が辞めてしまう又は取引先が取引を止めてしまうということが実際にどれぐらい起きうるのか、またそれが企業価値にどれだけの影響を与えるのかというのは、もう少し具体的に詰めていくべきではないのかということだと考えています。
対象会社において、余剰人員を抱えている場合又は非効率な仕入れを行っているような場合には、余剰人員をある程度整理すること又は取引関係を整理することが、対象会社の企業価値に必ずしも悪影響があるとは限りません。従業員や取引先との関係が重要だとしても、それは絶対的なものではないはずです。対象会社として、そういった定性的な事情に一切言及してはならないということはなく、また、その影響を常に定量的に金額で明らかにしなければならないわけではないと思いますが、買収者の提案が、予想される従業員や取引先への影響を上回る、企業価値の向上策を含んだものであるかが、買収提案の是非を判断する上での肝であると思います。対象会社の経営陣としては、より具体的に、本当に従業員が辞めるのか、従業員が辞めたところでどれだけの影響があるのかを詰める必要があると思います。
また、現金対価での全部買収の提案があった場合には、それが買収者側の買収後の企業価値への影響を受け入れるという覚悟を示しているのだとすると、対象会社が定性的で抽象的な悪影響を主張しても、あまり意味がないのではないかと思います。
- 飛岡
-
小舘弁護士にお聞きしますが、今の後藤先生のご意見は、定性的な事情を考慮することは問題ないが、その具体的な影響については、できるだけ具体化・定量化を試みるべきというご示唆と理解しましたが、実務上そのように対応していくことが可能か、実務家の観点からご意見はありますか。
- 小舘
-
まさにご指摘のとおりと思っております。私が実際に関与した案件でも、買収提案があった際に、買収者の競合相手である取引先が取引を止めてしまう確度がかなり高いということで、売上・利益の面でのネガティブなディスシナジーが生じると考えて、定量化を行った案件があります。ただし、通常は公表前の段階で取引先に取引継続の意向を聞くわけにもいかないため、定量化するために必要な確度並びにタイミング及びインパクト等の評価は、できないことはないものの、なかなか難しいように思いました。
従業員が辞めてしまうリスクの評価はより難しく、従業員一人一人が実際に辞めてしまうかどうかは不確定であり、また、後藤先生のおっしゃるとおり、対象会社において余剰人員を抱えている場合には、余剰人員の整理をすることが企業価値の向上につながることもありえます。具体的な事案の中でも、買収者が買収後の賃上げを提案していたため、コスト増となり、かえって企業価値の評価にマイナスの影響が生じてしまうということもありました。
なかなか悩ましく、定量化ということが一人歩きするのも違和感があるということは、実務家として思っているところです。
- 飛岡
-
そういう意味では、実務としてはできるだけ定量化を試みていくものの、定量化できない要素もどうしても残ってしまうということのように思います。そうした定量化できない部分が出てくる場合に、それも定量的なものとは別に対象会社において考慮すべき事項として残しておくことは許容されるのか、定量化できない曖昧なものは、できるだけ考慮から排除した上で検討を進めていくべきなのか、そのあたりについて、後藤先生、いかがでしょうか。
- 後藤先生
-
一言ではお答えしにくいところですが、おそらく一切考慮してはならないということまでは求めていないと思います。
定量化できないとしても、例えば、代替性のないスキルを有した従業員が辞めてしまう可能性が高いという場合、企業価値への影響額を具体化することはできないものの、それ自体が重要な情報ではあるので、株主が買収提案の是非を判断する上でも、対象会社から情報提供をした方がよいと思います。抽象的に従業員に不利益が及ぶというだけではなく、具体的な悪影響を詳細に説明することで、対象会社の経営陣が自己保身のために買収提案に反対しているのではないかという疑いは減っていくので、定量化できない定性的な事項についてもできる限り具体的に説明をするということでよいと思います。その上で、最終的には、そういった経営陣の説明も踏まえた上での株主の判断になります。
より悩ましいのは、複数の買収提案がある場合に、買収価格は低いものの、従業員の雇用維持を約束している買収提案について、対象会社として賛同できるかという問題ですが、対象会社の経営陣として、買収価格の低い買収提案の方が企業価値向上により資すると判断するのであれば、もっと高い価格を提案してもらうように交渉すべきではないかということに、つながっていくと思います。ですので、そこまでいくと、数字での定量化の話になると思いますが、対象会社として一般的に定性的な事項を考えてはならないということではないと思っております。
2. 「買収を行わなければ実現できない価値」に関する公正な分配のための交渉の在り方
本指針第2章「原則と基本視点」2.2.2「企業価値の向上と株主利益の確保」関連
(該当箇所の解説は、AMTニュースレター「企業買収における行動指針の概要②」7、8頁参照)
Q2 シナジーの分配方法(これまでの実務と今後の対応)
-
飛岡第1原則における「株主共同の利益」について、「買収が行わなければ実現できない価値」(いわゆるシナジー)に関して、公正に株主に分配すべきとされているが、具体的にどのように分配していけばよいのか。
➔ 分析・実務への影響
-
佐橋実務上は、対象会社がM&A(シナジー)を考慮せずにスタンドアローンの事業計画をベースに企業価値評価を行い、その枠内で算出された価格が、現在の株価に対して他社事例と比較して相当のプレミアムが付されものになっているかを確認していることが多い。シナジーを厳密に定量化して、どのように分配するというところまでを取り決めている例は、ほとんどないとの理解である。後藤先生現実にシナジーを算定できるかという点について、裁判においては両者から資料を提出させることもできるが、交渉の場面においては、買収者が手の内を見せることはない以上、対象会社側でシナジーの金額を具体化できないのはある意味当然である。最低価格ラインをある程度客観的に評価することができるので、スタンドアローンの事業計画がベースになり、対象会社においては、買収者側が考えるであろうシナジーを予想して交渉するというのは変わらないだろう。その上で、対象会社としては、できるだけ高い価格で買ってもらうとする姿勢を見せることが必要であり、例えば、マーケットチェックをした上で、他にも買手候補がいるということを見せるなどして、交渉力を確保するということが重要である。
今後の実務上の展開・残された課題
-
本指針においても示唆されているように、対象会社としては、できるだけ高い価格で買手に株式を買ってもらうための姿勢を見せることが必要であり、そのために、例えば積極的なマーケットチェックをするなどの行動が浸透していくか注目される。
Q2 シナジーの分配方法(これまでの実務と今後の対応)
- 飛岡
-
第1原則における「株主共同の利益」については、これまでの実務上の考え方と同じく、「買収が行わなければ実現できない価値」(いわゆるシナジー)に関して、公正に株主に分配すべきとされていますが、具体的にどのように分配していけばよいのでしょうか。本指針でも、具体的な分配の方法までは書かれていないと理解しております。まずは、佐橋弁護士にお聞きしますが、実務上、シナジーに関してはどのように評価をして、どのように買収者と他の株主とで分配しているのでしょうか。
- 佐橋
-
実務上は、対象会社がM&A(シナジー)を考慮せずにスタンドアローンベースの事業計画を作り、それに基づいて自らの企業価値評価を行いつつ、買収者側でも対象会社の企業価値評価を行います。それぞれが企業価値評価を一定の価格帯で算出し、それら双方における企業価値評価に基づいて、買収者と対象会社において価格交渉がなされ買収価格が決定されていることが多いように思います。また、一般的には、そのような交渉を経て買収者から提案された価格が、現在の株価に対して他社事例と比較して相当のプレミアムが付されものになっているかを、対象会社において確認していることが多いと思っております。その際に、シナジーを厳密に定量化して、どのように分配するというところまでを取り決めている例は、ほとんどないのではないかと理解しております。実務上、シナジーの定量化が難しいことが背景にあると考えております。
- 飛岡
-
実務上、企業価値評価の観点からは、スタンドアローンベースで企業価値評価を行い、提案された買収価格がその範囲に収まっているかを確認した上で、シナジーが公正に分配されているかについては、他社事例も踏まえてプレミアムが十分に付されているかを確認することが行われているものと理解しました。本指針としては、おそらくシナジーについてもう少し定量化した上で、それがどの程度プレミアムとして株主にも分配されているかといったところまで検討できれば望ましいということを提示しているものと理解しております。後藤先生にお聞きしますが、シナジーを定量化することが難しいということを踏まえて、スタンドアローンベースで企業価値評価を行っている現状の実務の運用について、本指針の観点から、ご意見はありますでしょうか。
- 後藤先生
-
株式買取請求権の公正な価格の判断においてもシナジーの公平な分配の議論が出てきますが、その場合には、例えば、2社が合併するのであれば、その2社の企業価値が合体することによって増える部分がシナジーであると説明をすることが多く、ここでも同じ考え方だと思います。ただし、現実にシナジーを算定できるかは別の問題だと思います。また、シナジーを実際に算定した場合であっても、裁判所が両者から資料を提出させることができる株式買取請求権の場面とは異なり、買収提案を受けて対象会社が交渉する場面においては、シナジー部分がどれだけあるかは買収者側の買収後の経営計画に依存するものであり、そしてそれは買収者側がどれだけ出せるかということにつながりますので、買収者が交渉に際してその手の内を対象会社に見せることはない以上、対象会社においてシナジーの金額を具体化できないことはある意味当たり前だと思います。
その上で、対象会社としてどうすべきかということですが、まずは、スタンドアローンでの事業計画に基づいて、売手目線での最低価格ラインをある程度客観的に評価した上で、それを前提として、買収者側が考えるであろうシナジーをある程度予想して交渉するということになるかと思います。
その上で、どこまで強気に交渉ができるかというと、他に買主候補がいるかどうかということと関わってくるため、その観点から、本指針においてもマーケットチェックという言葉が出てきているのではないかと思います。マーケットチェックをした上で、他にも買主候補がいることが相手にも見えると、どうしてもその会社を買いたい買収者としては、やはり価格の面で譲歩せざるを得なくなるように思います。
その意味においては、本指針は、実務の方法を変更して、まずシナジーを計算しなければならないと述べているわけではなく、プロセス自体は変わらないものの、対象会社として、できる限り株主に有利な条件になるように買収者と交渉すべきであるという姿勢を強調しているということだと思います。
3. 真摯な買収提案についての考え方
本指針第3章「買収提案を巡る取締役・取締役会の行動規範」3.1.2「取締役会における検討」関連
(該当箇所の解説は、AMTニュースレター「企業買収における行動指針の概要②」3~5頁参照)
Q3-1 本指針で明示された考慮要素が今後の実務に与える影響
-
飛岡真摯な買収提案の内容について、本指針では、①具体性、②目的の正当性、③実現可能性などが考慮要素として挙げられているが、真摯性の検討内容について今後実務が変わる可能性はあるか。
➔ 分析・実務への影響
-
小舘公正M&A指針においても、真摯な対抗提案であれば検討しなければならないとされていたため、対抗提案が真摯かどうかを検討することは実務上行われていた。ただし、公正M&A指針では、具体性、実現可能性、真摯性という3つの言葉の中身については述べられていなかった。本指針ではその点が明らかになったので、実務上はかなり影響が大きいと思われる。「真摯」という文言は、真摯ではないとの抽象的な理由により買収提案に反対する根拠となり得る文言であったが、本指針では、「目的の正当性」に置き換えられており、例えば具体的な経営方針を示さない場合等に問題になり得ることが示されているなど、真摯な提案とされるための要件については、ある程度整理ができているように思われる。後藤先生「具体性」と「実現可能性」の欠ける提案については、対象会社として真摯に検討を行わないということも納得しやすいのに対して、「目的の正当性」は慎重に検討する必要がある。3つの要素は同じレベルのものとは捉えにくい。また、あくまで各要素の総合考慮であるということと、恣意的に解釈して安易に退けてはならないということは、しっかりと受け止める必要がある。例えば目的の正当性について、全部買収なのであれば買収後の経営方針の詳細が示されていないことを問題とすべきではないということは、学界では繰り返し指摘されているところであり、部分買収の時には、それを言う余地はあるかもしれないが、真摯な提案ではないと評価できるかどうかは、場合によりけりである。
Q3-2 真摯性の確認にあたり対象会社の取締役会に求められる対応
-
飛岡対象会社の取締役会としては、真摯な提案かどうか判断するだけではなく、真摯な提案である可能性もあるが要件に照らしてもはっきりしないような場合に、真摯な提案であることを確認すべきであるのか。例えば、本指針の存在を把握していない外国の企業などが、一部要件が欠けるような買収提案を行ってきた場合に、取締役会として補充質問をした上で真摯かどうかを確認していくべきなのか。また、別の例として、対象会社からの情報提供がないと競争法届出等についての検討が進まないという場合に、対象会社として実現可能性を高めるために情報提供をすべきであるのか。
➔ 分析・実務への影響
-
後藤先生問題のケースは、どちらかというと具体性や実現可能性に疑問がある場合であり、その場合に、対象会社として、もう少し具体的な提案をするようにリクエストすることは差し支えない。買収提案者が本当に買収をする気があるのであれば再提示があるであろうし、何度話をしても具体的な提案がされないのであれば対象会社として当該買収提案を拒絶しても問題はない。ただし、株主の利益のために良い買収提案である可能性もあるため、基本的には、ある程度やり取りは必要と思われる。どれだけの情報をどの段階から出すかはケースバイケースである。
今後の実務上の展開・残された課題
-
本指針において、真摯な買収提案の考慮要素の一つとして「目的の正当性」が示されたが、その解釈にあたっては慎重な検討を要する。
Q3-1 本指針で明示された考慮要素が今後の実務に与える影響
- 飛岡
-
本指針第3章では「買収提案を巡る取締役・取締役会の行動規範」が定められており、真摯な買収提案の内容について記載されています。具体的には、①具体性、②目的の正当性、③実現可能性などが考慮要素になるとされています。公正M&A指針においても、真摯な提案については真摯に検討するという考え方自体は採用されていましたが、本指針ではかなり具体的な考慮要素が提示されている点が予見可能性の観点からは評価すべきところだと考えております。まず小舘弁護士にお聞きしますが、本指針が挙げているこれらの考慮要素について、従来から実務において検討されてきた項目なのか、それとも、新しい検討項目として今後実務が変わってくる可能性があるような項目なのでしょうか。
- 小舘
-
公正M&A指針においても、MBOなどの文脈ですが、対抗提案者が出現した場合に、その対抗提案が具体的かつ実現可能性のある真摯なものであれば、合理的な理由なくこれを拒絶することは適切とはいえないとされていました。そのため、これまでも、たとえMBOなどの文脈ではなくても、対抗提案が出てくるケースでは真摯な買収提案であるかどうかを検討することは実務上行われていたと思います。
ただし、公正M&A指針では、具体性、実現可能性、真摯という3つの言葉が使われていましたが、その中身については語られていなかったため、実務上は真摯に検討しなければならない提案とは何かという点について、やや混乱があったのではないかと思います。その点が本指針で明らかになりましたので、実務上はかなり影響が大きいところと思っております。
本研究会における議論で一番難しかった点は、「真摯」の点です。「具体性」の点はわかりやすく、「実現可能性」の点も、通常は買収資金の調達の可否と買収のために必要な許認可の取得の可否が主なポイントとなっていました。一方で、「真摯」という文言は、対象会社として買収提案に反対する場合に、真摯ではないとの抽象的な理由として持ち出す余地のある文言でしたが、本指針においては、「目的の正当性」に置き換えられています。
公正M&A指針の解釈において、「真摯」が「具体性」と「実現可能性」とは別の要件かどうかについても争いがあったのですが、本指針では、真摯性=目的の正当性も考慮要素の一つとされており、どちらかというと三要件説をとっているような記載になっており、また、「目的の正当性」について、例えば具体的な経営方針を示さない場合等に問題になり得ることが示されていますので、真摯な提案とされるための要件については、ある程度整理ができたものと思っております。
Q3-2 真摯性の確認にあたり対象会社の取締役会に求められる対応
- 飛岡
-
本指針によって、対象会社の取締役会としては買収提案が真摯な提案かどうかを検討しなければならないことが明らかにされましたが、それに加えて、真摯な提案である可能性もあるが、要件に照らして検討してもそれを満たすかはっきりしないような場合に、取締役会として、真摯な提案であるか確認する必要があるのかというところを議論させていただきたいと思っております。
例えば、本指針の存在を把握していない外国の企業などによる買収提案が、本指針に沿わない形でなされたため、一部の要件を満たさない可能性があるような場合に、対象会社の取締役会として補充質問をした上で真摯かどうかを確認していくべきなのか、それとも、ひとまず現状の提案では真摯な提案とは認められないと拒否した上で、再提案された場合に限り、もう一度検討することでよいのかという問題についてはいかがでしょうか。また、買収提案者において、対象会社から提供される情報がないと競争法等についての検討が進まず、実現可能性を満たさない可能性があるという場合に、対象会社として実現可能性を高めるために情報提供をすべきなのかといった問題も考えられます。
この点について、後藤先生はどのようにお考えになるでしょうか。
- 後藤先生
-
小舘弁護士からもご説明いただきましたけれども、本指針において「真摯」とは何かということが前よりもイメージが湧きやすく書かれたことは、おそらく実務にとって非常に大きなことであると思っております。ただし、「具体性」、「実現可能性」及び「目的の正当性」の3つの要素が同じレベルのものとは捉えにくいように思います。具体性と実現可能性の欠ける提案については、対象会社として検討を行わないということも納得しやすいのに対し、目的の正当性が合理的に疑われることを理由として対象会社として検討を行わないという判断をする場合には、本当にそれでよいのか慎重に考える必要があるように思います。
また、本指針では、あくまで各要素の総合考慮であるということと、恣意的に解釈して企業価値を高める提案を安易に退けてはならないとされていることも、しっかりと受け止めておく必要があると思います。例えば目的の正当性において、買収後の経営方針を買収者が示してしまうと真似をされてしまう可能性があるため、買収者として詳細までは示さないということもやむを得ないように思います。学界においては、全部買収では、買収後の経営方針の詳細が示されていないことを問題とすべきではないということが繰り返し指摘されております。部分買収の場合には、この点を理由として真摯な提案ではないと判断をする余地もあるかもしれませんが、対象会社として真摯な提案ではないと評価できるかどうかは、やはり場合によりけりということだと思います。
その上で、問題として提起された事例は、どちらかというと、具体性や実現可能性があるのかがよくわからないという場面かと思います。その場合には、対象会社として、買収提案者に対して、もう少し具体的な提案をするようにリクエストすることはもちろん差し支えないと思います。買収提案者として本当に買収をする気があるのであれば、もう少し話が進めば、買収提案者から提示があるはずですし、何度話をしても具体的な提案がされないということであれば、対象会社から検討を打ち切ると言っても問題ないと思います。
全く検討に値しない買収提案も、もしかしたらあるのかもしれませんが、株主の利益のために良い買収提案である可能性もあるので、対象会社としては、基本的には、ある程度やり取りをしていくことになるのだと思います。そのときに、対象会社として、どれだけ情報をどの段階から出すかというのははっきりとしたラインが引かれるものではなく、ケースバイケースということになるとは思います。
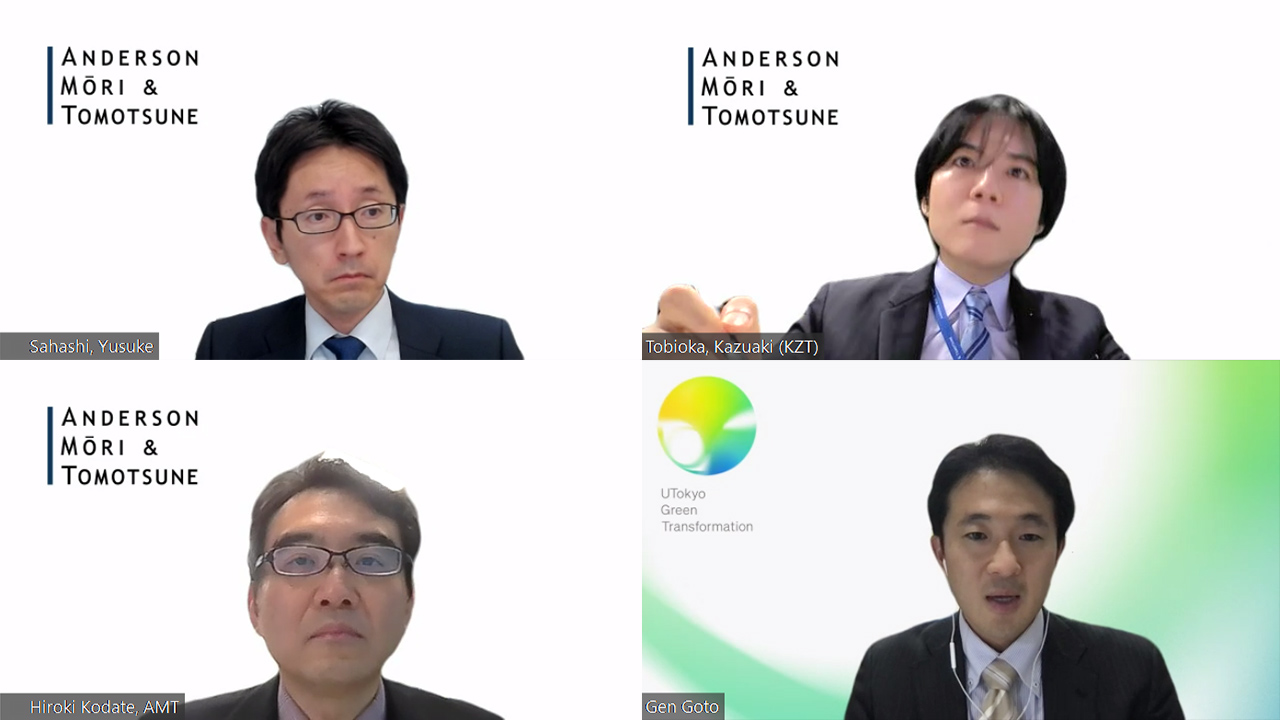
4. 取締役会が買収に応じる方針を決定する場合の交渉の在り方
本指針第3章「買収提案を巡る取締役・取締役会の行動規範」3.2.3「株主にとってできる限り有利な取引条件を目指した交渉」関連
(該当箇所の解説は、AMTニュースレター「企業買収における行動指針の概要②」6、7頁参照)
Q4-1 本指針3.2.3の規範とレブロン義務との比較
-
飛岡本指針においては、「取締役会が買収に応じる方針を決定する場合」には、対象会社の取締役会としては、買収者との間で企業価値に見合った買収価格に引き上げるための交渉を尽くすべきだといったことが挙げられている。アメリカのレブロン義務を念頭において定められたというような評価もあるが、レブロン義務と比較した上でどういった差異があるか。
➔ 分析・実務への影響
-
後藤先生アメリカのレブロン義務は、会社が身売りをすることを決めたら適用されると言われるが、本指針の場合には、身売りをすることはまだ決めていないとしても、交渉の指針として考えるべきことが書かれているという意味では、レブロン義務よりも適用されるタイミングが少し早いようにも思われる。レブロン義務そのものを持ち込んだというよりは、レブロン義務の背後にある、取締役は、企業買収の局面では株主の利益のために交渉するのが基本線であるという考え方を持ってきたという点で、レブロン義務を意識していると言われていると思われる。日本においては、それが共通理解として存在していたとは言い切れないところがあるので、当該考え方を持ち込んだという点については、積極的に評価すべきである。レブロン義務と異なり、具体的な行動まで導入されたわけではなく、基本的な考え方を明示したということだと思うが、他方で今後の実務の積み重ねによって、それが具体化されていく可能性もありうる。
Q4-2 本指針3.2.3の規範が今後の実務に与える影響
-
飛岡本指針を踏まえて実務にどのような影響があるか。また、トリガーされるタイミングが早すぎるのではないかといった問題はあるか。
➔ 分析・実務への影響
-
佐橋対象会社において売却をすることを決めた場合に、買収者との間で、企業価値に見合った買収価格にするための交渉を尽くすとか、部分買収であることによる問題が大きいと考える場合に全部買収への変更を含めて交渉するということは、これまでの実務でも意識して対応されていたところと思われるので、実務に大きな変更を迫るものではないと思う。ただ、行動規範として規定されたことにより、共有的に認識されるため、指針が定められたことの意義はある。
「買収に応じる方針を決定する場合」というのがいつなのかという点について、本指針で挙げられている例も踏まえると、経営支配権の移転を前提にしたような入札手続を実施するような場合や、対象会社側がイニシアティブを持って交渉を前向きに進めるような動きを始めた場合が、これに当たると思われる。他方で、対象会社が買収に応じることを決めた場合に価格を上げるということは、今までも意識して行われていたところなので、トリガーされるタイミングは、実務的にはあまり意識しないで進められていると思う。 今後の実務上の展開・残された課題
-
「取締役会が買収に応じる方針を決定する場合」に、今後、何らかの具体的な義務が形成されていく可能性も排除できない。その展開が注目される。
Q4-1 指針3.2.3の規範とレブロン義務との比較
- 飛岡
-
本指針では、「取締役会が買収に応じる方針を決定する場合」には、対象会社の取締役会として、買収者との間で企業価値に見合った買収価格に引き上げるための交渉を尽くすべきだと述べられています。この点は、アメリカのいわゆるレブロン義務を念頭において定められたという評価もある一方で、トリガーされるタイミング及び取締役・取締役会としてあるべき行動の内容において、レブロン義務とは少し異なる日本独自の行為規範なのではないかといった評価もあるところと理解しています。まずは、後藤先生にお聞きしますが、本指針のこのような規範は、レブロン義務と比較した上でどのような差異があるとお考えになりますでしょうか。
- 後藤先生
-
アメリカのレブロン義務自体、一言で説明することが難しい複雑な発展を遂げていますので、本指針の内容とレブロン義務を正確に比較するのはなかなか難しいところです。レブロン義務については、一般的に、会社が身売りをすることを決めたら適用されると言われているかと思いますが、本指針の場合には、身売りをすることはまだ決めていないとしても、交渉の指針として考えるべきことが書かれているという意味では、レブロン義務よりも適用されるタイミングが少し早いようにも思われます。
もっとも、それが、厳しすぎて悪いという話ではないと思います。アメリカにおいては、対象会社の取締役は株主のために交渉すべきであるという意識自体が大前提としてある中で、特殊な形態としてのレブロン義務が限定的な場合に適用されるということだと思います。本指針は、レブロン義務そのものを取り込んだというよりは、レブロン義務の背後にある、取締役は、企業買収の局面では、株主の利益のために交渉するのが基本線であるという考え方を持ってきたということだと思われ、その点が、本指針がレブロン義務を意識していると言われているところかと思います。日本においては、そういった意識が共通理解として存在していたとは言い切れないところがあるので、レブロン義務とは違う少し薄まったものであり、早く適用されうるものではあるとしても、そのような考え方を導入したという点は積極的に評価すべきと思います。レブロン義務を真似しなければならないわけではなく、逆に真似してはいけないというわけでもないので、日本のM&Aマーケットの状況に照らして、どういう行為規範を作っていくべきかという観点から評価すればよいと思っているところです。
- 飛岡
-
そういう意味では、レブロン義務では、より具体的にマーケットチェック等の行為内容まで考えられている部分もあるのに対し、本指針では、基本的に取締役会としてどのように考えるべきかという考え方を規定したものであって、一定の具体例は挙げられているものの、具体的にどういった行動をしなければならないのかについては、今後の実務においてケースバイケースで考えていくべきものであると考えることになるでしょうか。
- 後藤先生
-
本指針が、基本的な考え方を導入したものであり、より具体的にこういう時にはこうしなければならないといったところまでは書かれていないというのは、ご指摘のとおりかと思うのですが、他方で、今後の実務の積み重ねによって、それが具体化されていく可能性もまた排除されてはいないように思います。
マーケットチェックに関しては、アメリカのようにそれをやらなかったらアウトというところまで、日本においてすぐになるというところまでは行かないかもしれませんが、日本においても、マーケットチェックをやらないのであれば、なぜやらないのか、やらないことに合理性があるのかということが検討されていくことになるのかなと思います。本指針は、あくまで2023年時点のものであり、それでも、2019年に公正M&A指針ができてからわずか4年であるということを考えると大きな進展ではありますが、今後さらに進展して、将来的にはかなりレブロン義務と近い形になっている可能性も否定できないように思います。
Q4-2 本指針3.2.3の規範が今後の実務に与える影響
- 飛岡
-
同じ論点について佐橋弁護士にもお聞きしますが、実務において、本指針の考え方がどのような影響を与えるでしょうか。また、後藤先生がおっしゃっていたとおり、トリガーされるタイミングが、レブロン義務よりも早い可能性もありますが、実務上早すぎるのではないかといった点について、ご意見ありますでしょうか。
- 佐橋
-
まず、実務上どのような影響があるかという点ですが、対象会社において売却をすることを決めた場合に、買収者との間で企業価値に見合った買収価格にするための交渉を尽くすとか、競合提案があるような場合に競合提案に匹敵する程度に価格の引上げを求めるといったようなことは、これまでの実務でも意識して行われてきたところではないかと思います。部分買収であることによる問題が大きいと考える場合に、全部買収への変更を含めて交渉するということは、当然ながら買収者側の買収戦略等もありますので必ずしもうまく行くものではないですし、現実的にこの点を交渉のポイントとすることができないということもあると思いますが、いずれにせよ、先ほど申し上げたように、これまでの実務でもやはり意識して対応されていたところかと思います。その意味では、この点が実務に大きな変更を迫るものではないとは思います。他方で、やはり行動規範として一つ一つ書かれていくことによって、共有的に認識されることにはなるので、その意味では、指針が定められているということの意義はあろうかと思います。
レブロン義務と比較して早いのではないかという点については、そもそも「買収に応じる方針を決定した場合」がいつなのかという点が問題になりますが、本指針においては、「対象会社として積極的に経営支配権の移転にかかる買収提案を模索し、提案の選択や条件の設定の交渉に入った場合」と「経営支配権を取得する旨の買収者からの提案に応じる方向で合意に向けた交渉に入った場合」が挙げられています。前者については、典型的には経営支配権の移転を前提にしたような入札手続を実施するような場合が想定されているように思います。後者については、例えば、買収者側からTOBを前提とした買収提案がなされ、TOBに関する合意書についてやり取りが開始されたような場合、特に対象会社からそれに応じる形で返答、行動したといったように、対象会社側がイニシアティブを持って、交渉を前向きに進めるような動きを始めた時点で、「買収に応じる方針を決定した場合」にあたると考えています。ただ、先ほど申し上げたように、対象会社が買収に応じることを決めたような場合においては、価格を上げるということは今までも意識して行われていたところではあるので、どの時点からフェイズが変わるということは、実務的にはあまり意識しないで進められているかと思います。
5. マーケットチェックの在り方
本指針第3章「買収提案を巡る取締役・取締役会の行動規範」3.2.3「株主にとってできる限り有利な取引条件を目指した交渉」関連
(該当箇所の解説は、AMTニュースレター「企業買収における行動指針の概要②」7頁参照)
Q5 今後の実務におけるマーケットチェックのあるべき姿
-
飛岡マーケットチェックのあるべき姿について、どのように考えるべきか。
➔ 分析・実務への影響
-
後藤先生日本において、これまでは対抗提案が出ることもまれであったが、対象会社として対抗提案を真摯に検討するという行動が一般的になっていくと、対抗提案が増えていくと思う。対抗提案が増えていけば、間接的なマーケットチェックであったとしても、マーケットチェックとして十分であるとも言いやすくなってくるが、日本のマーケットの現状として、待っていれば誰かが対抗提案出してくれるという環境にあるとまでは、まだ言えないと思われる。このような状況を踏まえると、対象会社として、積極的に買主候補を探していくことも必要になってくる場面もある。本指針は、特定の手続を踏まなければならないとは規定されていないが、特定の手続を踏まないのであれば、その合理性について説明がつけられるようにという点は今後意識していく必要がある。小舘積極的なマーケットチェックが難しいのは情報漏洩のリスクがあるということにある。それによって株価が上がってしまうと取引ができなくなることにもなりうる。ディールを実現するという関係者全体の利益のためにも、かなり慎重にならざるを得ない。他方で、実務家の感覚としても、対抗提案は今後増えてくるという気もしている。もっとも、対抗提案者の立場で考えると、現状の公開買付制度及び実務では対抗提案を行うまでの時間が限られていると思われる。非公開化案件では、公開買付期間を30営業日とすることが一般的だが、対抗提案者としては、競争法等の手続の関係上、その期間内に公開買付け自体を開始することは難しく、とりあえず公開買付けの開始予告までを実施することになるが、それでもなかなか厳しい。特に買収資金を金融機関から調達するような案件においてはなおさらである。そういう意味で、間接的なマーケットチェックをしっかりと機能させるためには、対抗提案者側の立場では、公開買付期間は対抗提案を出すのに無理のない程度には長くしないといけないと思うが、先行買収者側で考えると取引の安定性の観点からは、できる限り公開買付期間は短くしたいという考え方もある。そういう意味では、積極的なマーケットチェックが不要となる程度に間接的なマーケットチェックが十分に機能しているといえるためには、30営業日だと少し短くて、もう少し長いのがフェアじゃないかと思う。後藤先生公開買付期間の大きな問題と思う。また、逆に言うと、公開買付期間を30営業日としてしまうこと自体が、対抗提案の機会を十分に与えずに進めようとしているとして、間接的なマーケットチェックができてないという評価をされる可能性もあるのかもしれない。
今後の実務上の展開・残された課題
-
対抗提案が増加することにより、間接的なマーケットチェックが行われているという環境が作られていくのか、それとも、積極的なマーケットがより積極的に行われていくようになるのか、また、公開買付期間が長めに設定されるという変化をもたらすのか注目される。
Q5 今後の実務におけるマーケットチェックのあるべき姿
- 飛岡
-
先ほども後藤先生からご指摘があったマーケットチェックについて、本指針では、実施することが望ましいとまでは書かれず、実施することにより買収条件の改善を目指すことにも合理性があると書かれています。後藤先生にお聞きしますが、マーケットチェックのあるべき姿について、本指針を踏まえてご意見ありますでしょうか。
- 後藤先生
-
対象会社として、積極的に対抗的な買主候補を探すべきかどうかというところだと思います。
そもそも日本においては、対抗提案が出されること自体がほとんどなかったところ、2020年のニトリによる島忠の買収の件のように、対抗提案が少しずつ起きるようになってきました。日本においても、対抗提案が行われ、それを対象会社として真摯に検討するという行動が一般的になっていくと、おそらく対抗提案が出されるケースが今後増えていくと思われ、そのような環境になれば、間接的なマーケットチェックがしっかりと機能していくということになると思います。もっとも、日本のマーケットの現状として、待っていれば誰かが対抗提案を出してくれるという環境にあるとまでは、まだ言えないように思います。そのような日本のマーケットの現状を踏まえると、対象会社として、ある程度積極的に買主候補を探していくということも必要になってくる場面があるというのは否定できないように思います。特に、最初から特定の買主候補とだけ交渉をするというのは、対象会社の株主に対して説明がつきにくい場合はあるように思います。もちろん、本指針は、特定の手続を踏まなかったからアウトだということにはなっていませんが、対象会社の経営陣として、株主に対して特定の手続を踏まなかった理由を説明できるようにしておかなければならないというのが、本指針の大きな考え方だと思いますので、そこは今後意識していく必要はあるのかなという気はしています。
- 小舘
-
後藤先生のご指摘のとおり、実務家の感覚としても、対抗提案をしてもよいんだという機運が高まっているように感じており、今後も増えてくる気もしております。
実務上、積極的なマーケットチェックを公表前に行う上で難しいのは、マーケットチェックをすることにより情報が漏れてしまうことにあると思います。それによって株価が上がってしまうと取引ができなくなることにもなってしまいます。ディールを実現するという、対象会社の株主を含めた関係者全体の利益のためにも、積極的なマーケットチェックまで行い多数の関係者に声をかけるというのは、やはり、かなり慎重にならざるを得ないように思います。
もっとも、5年ほど前と比べると本当に考えられないようなペースで対抗提案を含めたM&Aの実務が動いてるように思いますので、そうなってくると、確かに積極的なマーケットチェックまでしなくても、開示した後に対抗提案が出てくるということになるように思います。
一方で、対抗提案者の立場で考えると、現状の公開買付制度及び実務では対抗提案を行うまでの時間が限られているように思います。実務上、非公開化案件では公開買付期間を30営業日とすることが一般的であり、対抗提案者としては、対抗提案をするためには、少なくともその期間内に公開買付けの予告をすることが必要です。その期間内に公開買付け自体を開始することは、競争法等の手続の関係上難しく、とりあえず公開買付けの開始予告までを実施することを目指すことになるのですが、予告であっても30営業日ではなかなか厳しいように感じております。特に買収資金を金融機関から調達するような案件においては、金融機関との交渉を含めると30営業日はぎりぎりのように思います。そのような意味において、間接的なマーケットチェックをしっかりと機能させるためには、公開買付期間に係る規制及び実務が今のままでよいかは検討が必要かもしれません。
- 後藤先生
-
ご指摘のあった、実務上一般的に公開買付期間として設定されている30営業日が短すぎるという点は、確かに大きな問題なのかなと思いますし、逆に言うと公開買付期間を30営業日としてしまうこと自体が、そういう意味ではネガティブに評価される可能性というのもありえるのかもしれません。だからといって、最短期間を45営業日などにするのがよいのかどうかまたよくわからないところもありますが、30営業日で設定して対抗提案の機会を十分に与えずに進めようとしていることをもって、間接的なマーケットチェックができていないという評価をされる可能性もあるかもしれないと思いました。
- 小舘
-
対抗提案者側で考えると、公開買付期間は、対抗提案を出すのに無理のない程度には長くしないといけないと思うものの、一方で、先行買収者側で考えると、やはり取引の安定性の観点からできる限り公開買付期間は短くしたいという考え方があるのも事実です。そのような意味では、積極的なマーケットチェックを不要とする程度に間接的なマーケットチェックが十分機能しているといえるためには、30営業日だと少し短くて、もう少し長いのが両者にとって公平なのではないかと思います。
- 後藤先生
-
40営業日とか先ほどの話だとそれぐらいということですかね。60営業日とかは長すぎるんでしょうね。
- 小舘
-
おっしゃるとおりだと思います。

後藤元 教授
関連コンテンツ
第2回もぜひご覧ください。






