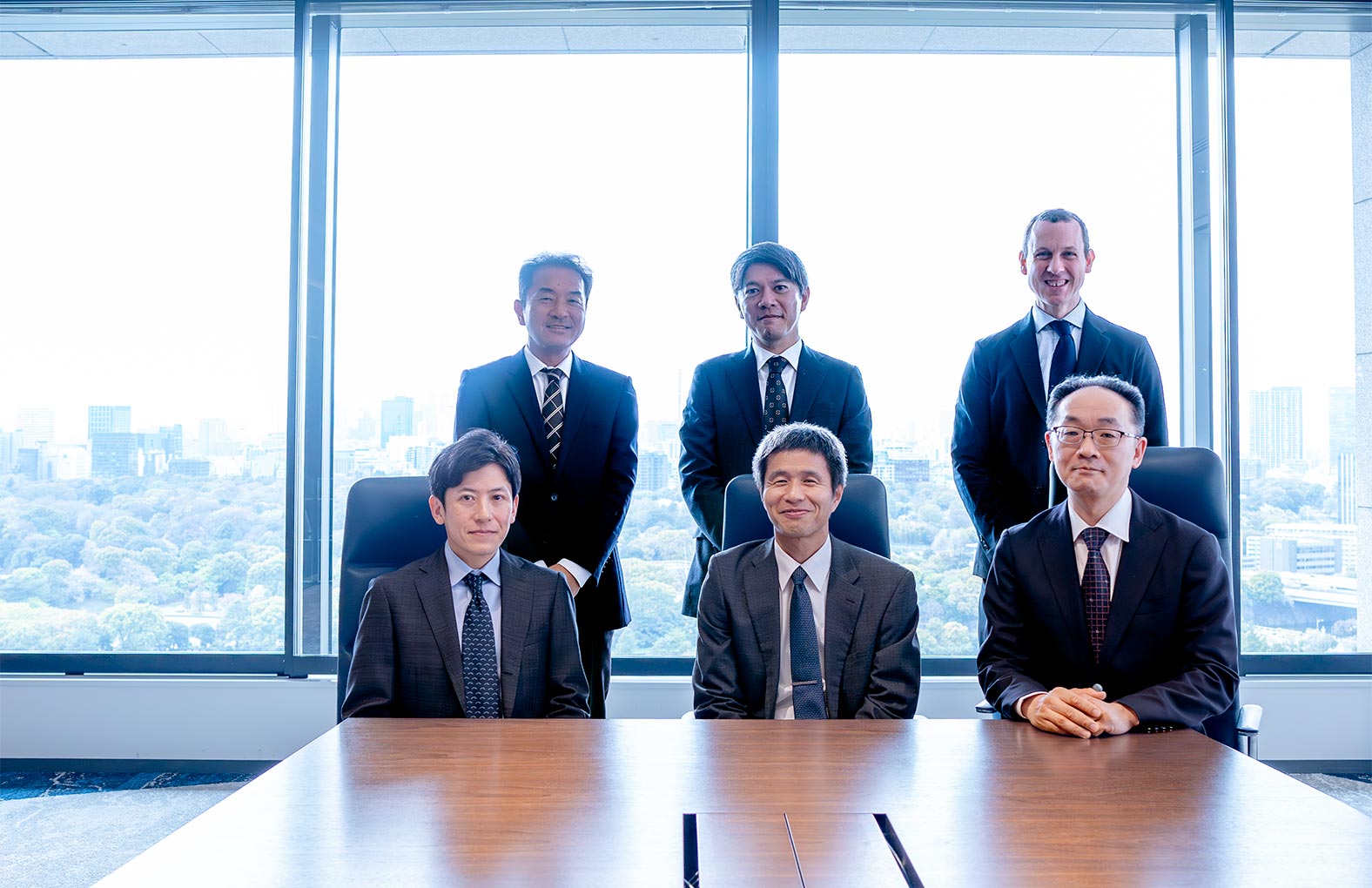第1回の「エネルギー分野に関する世界の潮流と日本企業の海外展開」、第2回の「国内再生可能エネルギー市場の最新動向-太陽光発電を中心に-」に続き、本シリーズ最終回となる今回は、国内エネルギー市場における蓄電池、洋上風力、M&A、原子力など幅広いトピックについて議論します。再生可能エネルギーの導入拡大が進む中で、日本のエネルギー・トランジションがどこまで進んでいるのか、そして今後どのような展開が期待されるのかを、多角的な視点から探っていきます。
対談参加者
1. 蓄電池ビジネスの拡大:3つのビジネスモデルとファイナンスの現状
武内 : 蓄電池については、長期脱炭素電源オークションの結果が出たころから一気に案件が増えたという印象です。
髙橋
:
蓄電池ビジネスには現在、大きく3つのモデルが出てきています。1つ目は電力広域的運営推進機関(「OCCTO」)からの容量収入で事業を回していくものです(OCCTO型)。2つ目は蓄電設備の運用権をオフテイカーに提供するトーリング契約を締結し、いわば設備の貸出しのような形態をとります(トーリング型)。3つ目は蓄電設備を所有・運営するSPC自身が電力取引を行うものです(マーチャント型)。
ファイナンス面では、OCCTO型は支払元の信用力が高く、比較的ファイナンスが付きやすいです。トーリング型は蓄電池設備の保有者が市場価格変動リスクを負わないため長期ファイナンスに適していますが、契約相手の信用力が十分に高い必要があり、そういったプレイヤーは限られています。マーチャント型は将来の電力価格がどう変動するか読みにくいため、金融機関は長期ファイナンスの可否についてまだ試行錯誤の段階です。
今後も事業の組み方やファイナンスの付け方について様々なパターンが出てくるでしょう。法律家としては、クライアントの多様なアイデアに対応していくことが重要になります。

前山 : 蓄電池についても太陽光と同様、複数物件をポートフォリオとしてまとめて取り扱う案件も出てきていますね。法律事務所の仕事としては、デューデリジェンスなどの需要が増えていくと思います。
横井 : 蓄電池については、長期脱炭素電源オークションや補助金など、事業者が政府支援を利用して事業展開する際の法的サポートのニーズが高いですね。蓄電池に限らず、水素やCCS(Carbon dioxide Capture and Storage:二酸化炭素回収・貯留)についても政府支援制度が導入されつつあり、この傾向は続くと思います。
2. 洋上風力の進展:資金調達、事業課題、撤退対応
髙橋 : 陸上風力は相変わらず底堅く案件があります。今後のメインは洋上風力でしょう。規模の大きな案件がいよいよ本格的に資金調達段階に入るため、そのファイナンスのサポートが昨年から今年にかけて大きな流れとしてあります。
横井
:
洋上風力はラウンド2以降、多くの落札者が出て、本格的な着工に向けた事業活動が活発化しています。物価上昇や為替変動の影響で事業採算性が当初想定から大きく影響を受けており、そうした中で、コーポレートPPAの活用や機器調達・建設面での工夫など、事業者の取り組みを法的側面からサポートしています。
また、近年の動きとして、海外の洋上風力事業者の中には日本で事業を継続する企業と撤退する企業の両方が出てきています。この動きに関する法的サポートのニーズも高いと感じています。
3. 再エネM&A市場の変化:大型案件の収束と中規模・ポートフォリオ売却の継続
武内 : 国内では、ENEOSによるJRE買収のような大型のプラットフォームM&Aは一段落した印象です。今後事業を本格的に継続する意思のある事業者が主要プラットフォームを取得した状態と言えるでしょう。
小林 : 海外投資家が保有するポートフォリオの売却は引き続きあるかと思います。単なる発電所の売却だけでなく、O&M会社(Operation and Maintenance Companies:運用保守会社)や日本人スタッフも含めた包括的なトランザクションも散見され、M&A色が濃くなってきています。こうした場面では、コーポレート部門の弁護士と連携して対応しています。

前山 : 対象会社が多くの発電所を保有している場合、M&A時のデューデリジェンスでどこまで見るかが問題になりますね。案件の実質を理解した上でリスク評価やスコープ設定を行うことが求められるため、エネルギー分野に精通した弁護士の価値が発揮される場面です。
髙橋 : デューデリジェンスの手法も技術や案件タイプによって変わってきます。太陽光発電については蓄積された知見があるため、ある程度リスク感が共有されており、ポートフォリオ取引ではスコープを絞る判断もしやすいです。一方で、風力や蓄電池はまだ案件数が少ないため、同じようなアプローチは難しいと思います。
横井 : 投資主体によっても今後の動向は異なります。インフラファンドはエグジット前提で投資しているため、今後もどこかの段階で売却に向けた動きをとることになるでしょう。また、最近の国内大手事業者と海外大手事業者による洋上風力分野での合弁会社設立のように、戦略的提携を通じて規模を拡大する動きも、今後の市場環境次第では見られると思います。
4. 原子力政策の転換:第7次エネルギー基本計画の影響の有無

ハーン : 2025年2月に閣議決定された日本の第7次エネルギー基本計画で原子力エネルギーについて「可能な限り原発依存度を低減する」という文言が削除され、「最大限活用する」方針が示されましたが、原子力分野での日本のマーケットの動きはいかがでしょうか。
横井 : 原子力発電を運営している会社では、再稼働したプラントは収益性が向上しており、積極的に稼働させる方向にあります。一方、これから再稼働を目指す施設は、地元との調整などで依然として困難を抱えています。
髙橋 : 日本では、原子力はマーケットの世界にはストレートには入ってこないカルチャーがあるように思います。
小林 : 原子力のプレイヤーは非常に限定的です。また、政府は原子力も再エネも両方推進すると言っていますが、再エネ事業者の中には、再エネへの支援が減るのではないかという懸念をもつ人もいるようです。
髙橋 : その点は、AIやデータセンターの需要により電力供給の絶対量を増やす必要があるため、ゼロサムの話ではないという理解でいます。限られたパイを奪い合うのではなく、パイ自体が大きくなっていくという見方です。
横井 : 第6次計画と第7次計画の最大の違いはそこにあると思います。第7次計画では電力需要が伸びるという見方に転換しています。まだ市場は様子見の段階ですが、大きな変化です。
5. その他の電源の現状:水素・CCS・水力・地熱・LNGの課題

髙橋
:
水素やCCSについては、国内では国の補助金を活用した実証事業のレベルにとどまっています。価格差支援などの制度を通じてパイロット事業を積み上げ、徐々に自立した事業形態を目指す段階です。
例えば、浄水場建て替えの際に自治体がGX実現のために水素施設設置を条件とするケースも出てきており、中長期的には継続的な産業として発展する可能性があります。
横井 : 自治体が小売電気事業に参入したり、再エネや水素導入に注力する事例が増えてきていると感じますね。
髙橋 : 水力発電については、既存事業者が自己資金で設備更新を行うケースが多く、外部投資家が参入できる機会は限られています。小水力案件も存在しますが、規模が小さいため大規模な投資にはつながりにくいのが実情です。
横井 : 水力発電業界全体では、既存施設にFIT/FIPを適用するという動きがありますが、多くは大手事業者が自社で対応しており、外部専門家の関与は限定的ですね。
髙橋 : 特にダムの水力発電施設では、内部構造に関する情報が既存運営者にしかわからず、設備更新期を迎えても、施設の状態を適切に評価できないことが新規資金の導入を難しくしています。加えて、水利用に関するルールや専門知識も求められ、参入のハードルは高いといえます。
武内 : 地熱発電については、開発に時間がかかることや、蒸気の安定性や発電量の正確な測定が難しいといった技術的な課題があり、必ずしも順調に進んでいるとは言えません。また、国立公園に関する規制や温泉権との調整といった外部要因も大きな障壁となっています。それでも、この分野に強みを持つ一部の事業者は、引き続き地熱発電の開発に取り組んでいます。
横井 : 燃料のコンバージョン(既設の改修)案件については、長期脱炭素電源オークションを利用して、LNG・水素の混焼プラントに建て替える案件や、石炭火力発電所をアンモニア混焼とするために一部施設を改修する案件などに取り組んでいます。
武内 : 長期脱炭素電源オークションを利用した案件であれば、レンダー側としては安定収入が見込めるため、ファイナンスを提供することが可能かと思います。ただ、脱炭素化のロードマップや運営リスクなどのモニタリングは重要になってくるように思います。
【おわりに】
全3回にわたる座談会シリーズを通じて、エネルギー・トランジションの世界的潮流から日本の市場動向まで、幅広い視点で議論を重ねてきました。最終回となる今回は、蓄電池ビジネスの新たな展開、洋上風力の本格着工に向けた動き、M&A市場の変容など、多様な電源の現状と課題を共有しました。複雑な課題が残る一方で、技術革新や政府支援を通じて日本のエネルギー・トランジションは着実に進展しています。本座談会が持続可能なエネルギー社会の実現に向けた一助となることを願い、シリーズを締めくくります。

関連コンテンツ
座談会:エネルギー・トランジションの最前線の第1回、2回も、ぜひご覧ください。
「資源・エネルギー」業務のご紹介