
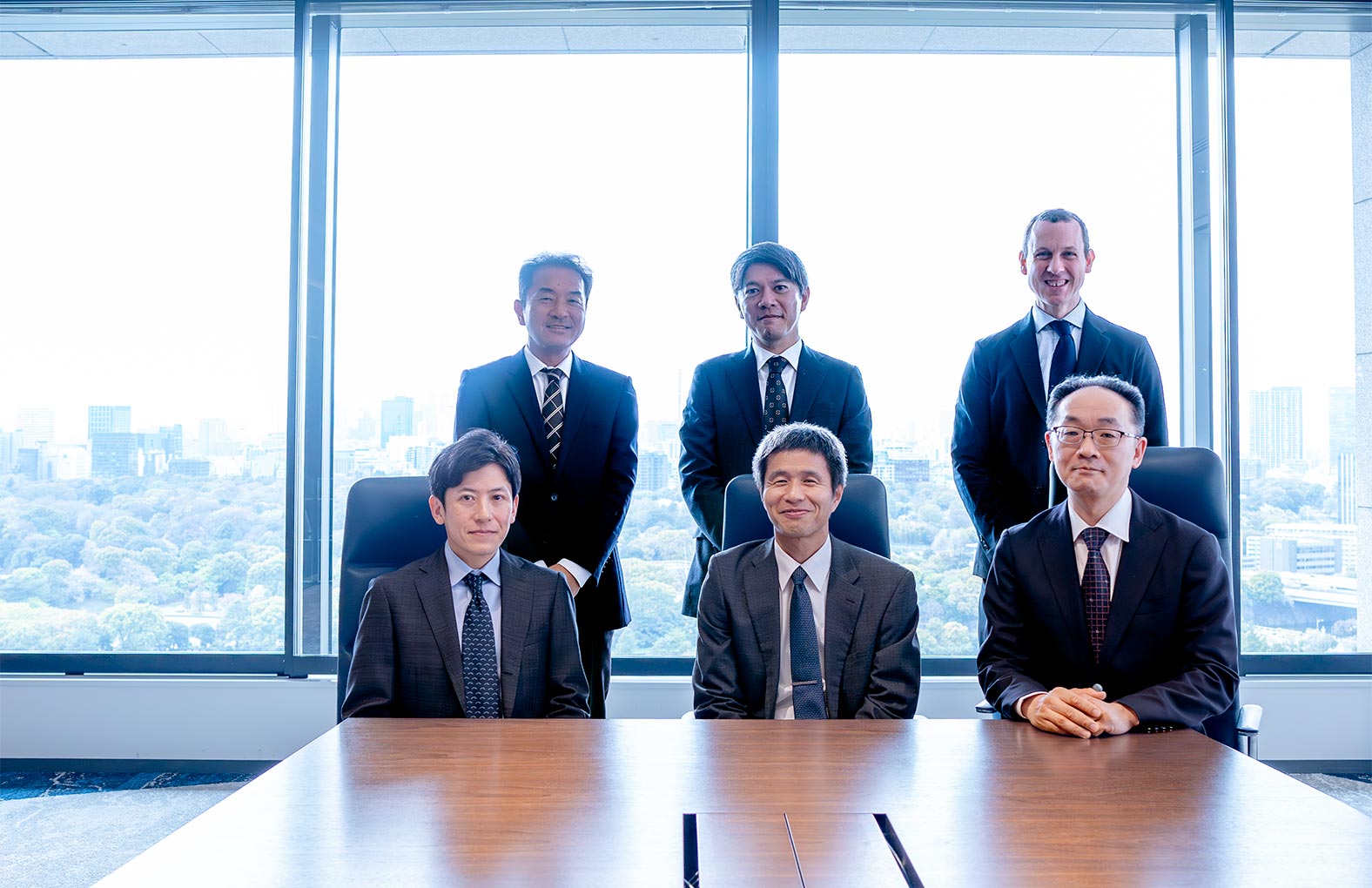
脱炭素社会の実現に向けた世界的な機運の高まりを背景に、クリーンエネルギー分野は急速に発展しています。本座談会では、クリーンエネルギー分野に精通した6名の弁護士が「エネルギー・トランジションの最前線」をテーマに、実務で直面する主要な課題や今後の展望について意見を交わしました。第1回は、エネルギー分野における世界のトレンドを整理した上で、市場の現状と日本企業の海外展開における課題に迫ります。
対談参加者
1. エネルギー分野に関する世界の潮流―8つの主要トレンド

ハーン
:
エネルギー・トランジションに関しては世界的に8つのトレンドがあると考えています。
1つ目は、2024年においてクリーンエネルギーへの投資がこれまでになく拡大し、化石燃料への投資額のほぼ2倍となり、初めて2兆ドルを突破したという点です。これは、脱炭素社会に向けた本格的な資本移動を示す、歴史的な出来事だといえるでしょう。
2つ目は、世界的な電化(electrification)へのシフトに伴い、電力の供給と需要が共に拡大し続けている点です。供給面では、稼働を開始する再エネ発電プロジェクトがどんどん増えており、様々な電源での新規発電プロジェクトも多数立ち上がっています。再生可能エネルギーに限らず、新規化石燃料プロジェクトの計画も多く、特にSMR(Small Modular Reactor:小型モジュール炉)や核融合など新技術の登場を背景に、原子力の再評価も進んでいます。こうした多様な電源により、今後も電力供給の増加が続くと見込まれます。
需要面では、AI(Artificial Intelligence:人工知能)、EV(Electric Vehicle:電気自動車)、データセンターの急増、社会全体のデジタル化、さらに新興国における中間層の拡大などを背景に、今後も世界的な電力需要の拡大傾向は続くと見込まれます。
3つ目は、洋上風力発電の停滞と、太陽光発電の加速度的な成長です。洋上風力は、多くの国で政策や規制の不十分さやサプライチェーン上のボトルネック、そしてコストの高騰といった課題に直面しています。一方、太陽光発電は、世界的に導入が加速しています。2024年に新たに導入された発電容量のうち、80%が再生可能エネルギー(約700GW)で、そのうちの80%を太陽光発電が占めていました。このように、洋上風力が伸び悩む中、太陽光が主力電源としての地位を強めている傾向は、日本においても共通しているかと思います。
4つ目は、再エネ分野でのM&Aの活発化です。エネルギー業界全体のM&Aを見ても、世界的に再エネ分野が最も活発であり、化石燃料関連M&Aを大きく上回っています。個別プロジェクトではなく、複数のプロジェクトを束ねたポートフォリオの買収が増加しており、より多様なプレイヤーが参入するようになってきています。日本企業の間でも、海外の再エネ分野でのM&A案件に対する関心が高まりを見せています。

ハーン
:
5つ目は、ネットゼロ目標の見直しに伴い、LNG(Liquefied Natural Gas:液化天然ガス)を含む石油・ガスや原子力が再評価されている点です。エネルギーの移行が当初想定より遅れる可能性が高まり、期限内でのネットゼロ目標達成が困難だという見方が広がっています。
その結果、LNGや原子力が当初の想定より長くエネルギーミックスに残る見通しとなっています。これは日本の最近発表した第7次エネルギー基本計画にも反映されていますね。さらに、日米首脳間の最近のやり取りで、日本が米国からのLNG調達量増加に前向きな姿勢を示したことも、日本企業による海外LNGプロジェクトへの投資拡大やLNG調達の増加の後押しとなりそうです。このような動きを受けて、私自身も最近、海外の売主とのLNG長期契約による新規LNG調達について、日本企業にアドバイスしました。
こうした状況の中、化石燃料を含むエネルギーミックスの継続を前提に、CCS(Carbon dioxide Capture and Storage:二酸化炭素回収・貯留)やCDR(Carbon Dioxide Removal:二酸化炭素除去)といった技術の重要性が一層高まっています。
また、ネットゼロ目標の見直しの流れの中で、ここ数ヶ月の間に、米国やカナダの銀行に続き、日本の銀行もNZBA(Net-Zero Banking Alliance)から撤退する動きが見られています。
6つ目は、電化に伴い、レアアースを含む重要鉱物(critical minerals)の保有やアクセスをめぐる競争が激化しているという点です。米国大統領がウクライナやグリーンランドの重要鉱物に近年注目していることからも、重要鉱物の必要性が地政学に影響を与えていることがわかります。こうした国際的な動向に沿って、日本企業も、重要鉱物に特化した鉱山プロジェクトへの新規投資を模索しており、私自身も最近、オーストラリアへのこうした投資案件の法的支援に関与しています。
7つ目は、蓄電池プロジェクトの普及です。蓄電池の導入は国内外で加速しており、再エネ発電設備とセットの併設型プロジェクトの方が、独立型に比べて一般的になっています。蓄電池は、再生可能エネルギー発電の出力が不安定に変動する性質に対応して安定した電力供給を確保する上で重要な役割を果たし、電力系統に安定性と柔軟性をもたらすため、エネルギー分野における不可欠な要素として台頭しています。
最後に8つ目、水素への関心がやや冷え込んでいることです。世界的に見ると、水素に対する関心や熱意がやや落ち着きを見せ、かつてのように「夢の技術」として語られることは少なくなっています。その代わりに、技術的・経済的な実現可能性に即したより現実的な視点が広がっています。それでも日本では、政府が水素社会の実現に明確な政策的コミットメントを示していることもあり、企業の関心は依然として高く保たれています。実際に、私は現在、海外で進行中の大規模なグリーン水素・アンモニアプロジェクトについて、日本のクライアントにアドバイスを行っています。
2. 地域別に見るクリーンエネルギー開発の特徴

前山 : 世界全体のトレンドを体系的に整理されていてよく理解できました。これらのトレンドは地域によって現れ方が異なると思いますが、世界の各地域ではどのようなエネルギー開発の特色が見られるのでしょうか?
横井 : 洋上風力や再エネ技術については、欧州で最初に発展し、その後アジアへ展開するパターンが多く見られます。水素事業については、欧州、中東、オーストラリアなどが中心となっています。特に中東は政府による強力な支援があり、大規模プロジェクトが進んでいます。例えば、世界初の大規模グリーン水素プロジェクトもサウジアラビアでスタートしました。
3. 日本企業による海外展開
武内 : 世界的なトレンドや地域ごとの特徴は、日本企業の戦略や海外展開にどのような影響を与えているのでしょうか。
横井
:
私たちがサポートする日本企業の間では、海外プロジェクトへの関心が確実に高まっています。国内市場での採算性に限界が見える中、海外展開に魅力を感じる企業が徐々に増えており、積極的に事業拡大を図るクライアントも増えてきたという印象です。
従来は、先端技術を日本に持ち帰るため洋上風力等の先進的プロジェクトに関与する事業者や、アジアでの収益性の高い事業に注力する事業者が多い傾向がありました。この基本的な方向性は今も続いていますが、対象範囲は徐々に広がっています。例えば、洋上風力の中でも、浮体式への投資も増加しています。
アジア地域では、ネットゼロ目標の影響で再生可能エネルギー事業への関心が高まっており、特に規模を見込める水力発電がインドネシアやフィリピンなどで進展しています。実際、昨年インドネシアで日本企業が手がけたプロジェクトには当事務所も関与しました。ベトナムでは引き続き太陽光や風力案件が多く、当事務所のベトナムオフィスも対応しています。海外案件については、当事務所の海外オフィス、特にインドネシアやベトナムのチームと共同して対応することも多いです。

横井
:
洋上風力に関しては、韓国やオーストラリアでも案件が出てきていますが、これらの市場への日本企業の本格参入はまだ早いかなと思います。ヨーロッパでは引き続き洋上風力の大規模プロジェクトへの投資や浮体式の実証事業が完了に近づいているケースもあり、日本の事業者が最先端の開発事業者とより深い提携関係を構築しようとする動きも見られ、そのような場面で当事務所がサポートさせていただいています。
最近の大きな動きとしては、グリーン水素の展開があります。太陽光、洋上風力、陸上風力と組み合わせて水素を生産するプロジェクトが増加しており、日本企業もこうした分野に関心を示しています。中東、米国、オーストラリアでは太陽光発電の開発も活発です。
M&Aについては、日本企業による個別プロジェクトを前提とした事業体への投資、ポートフォリオ投資、成長性を求めた現地開発企業の買収など、様々な形態が見られます。ただし、現地でのオペレーションは簡単ではないため、初期段階ではマイノリティ出資から始め、現地企業と提携関係を構築する傾向があります。こうした提携に関する契約書の作成などの相談も増えています。
また、再エネ技術に必要な鉱物資源への投資に注目する日本企業が増えていますね。メーカーやエネルギー事業者が従来型の燃料以外にも鉱物資源への投資を拡大しており、そのサポート案件も増加しています。
髙橋 : 政府支援の観点からも興味深い動きがあります。e-fuelなどの新しい燃料を製造する海外企業に日本企業がジョイントベンチャーで参画する際、政府系金融機関が出資金を支援するケースが出てきています。政府も最先端技術を早期に獲得し、国内に技術移転することを後押ししているのです。政府系金融機関や政府系支援機構へのアドバイスも当事務所の重要な業務の一つとなっていますね。
小林 : 海外の小規模エネルギーテック企業への早期投資という動きは確かに増えているように思います。これは日本企業が技術革新の波に乗り遅れないための戦略的な動きとも言えるでしょう。
【おわりに】
第1回は世界のエネルギー・トランジションの潮流から日本企業の海外展開まで、幅広い視点で議論を交わしました。8つの主要トレンドという分析枠組みから始まり、地域別の特色、そして日本企業の具体的な戦略まで、クリーンエネルギー分野の最前線についてお伝えしました。次回は国内の再生可能エネルギー市場の動向、特に太陽光発電に焦点を当て、さらに議論を深めていきます。
関連コンテンツ
座談会:エネルギー・トランジションの最前線の第2回、第3回も、ぜひご覧ください。
「資源・エネルギー」業務のご紹介














